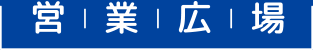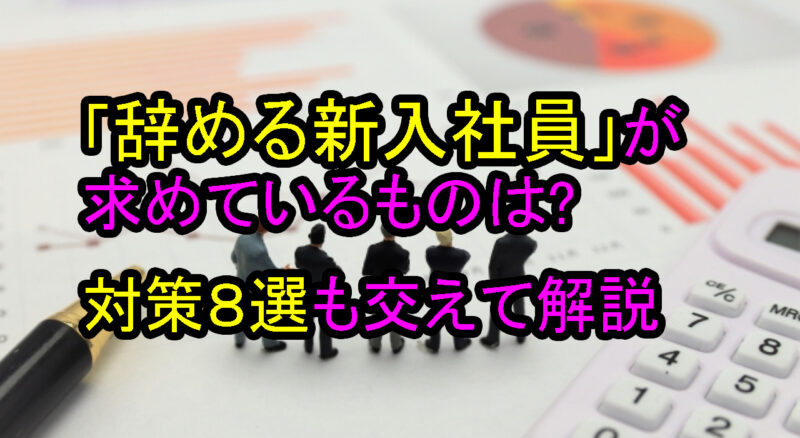こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!
いつの時代にもあるとはいえ、人も時間もコストもかけて採用した新入社員が辞めるのをどうにかして防ぎたいと思いませんか?
今回は自分たちとは違う新しい時代の若者が新入社員として会社に求めているものと、そんな新入社員の退職を防ぐためにどのような対策をしていくべきなのかをご紹介いたします!
目次
新入社員が辞める原因は「やりがい・達成感」の欠如

冬が明ければ新入社員が入ってくる春がやって来ます。
しかし長い時間とコストをかけて採用した新入社員も、大卒の場合3年以内に3割が辞めるという事実が根強く残っています。(高卒は4割、中卒は6割)
新規学卒者の離職状況
引用元:厚生労働省
しかし、実際は新入社員の早期退職は職種に因るところも大きく、SE、外食・施工関係、量販店など、昔から離職率の高い職種も存在します。
中には「この仕事は新入社員には非常に厳しい・・・。」という配属のミスもあるようです。
退職理由はある程度同じ
早期退職にはそれぞれの状況があるかと思いますが、その主たる理由というものはある程度共通しています。
今回はエン・ジャパンが2019年9月に行った調査から読み取っていきたいと思います。
1、「給与が低かった」(46%)
2、「やりがい・達成感を感じない」(43%)
3、「人間関係が悪かった」(34%)
4、「企業の将来性に疑問を感じた」(34%)
5、「残業・休日出勤など拘束時間が長かった」(33%)
きっかけは「やりがいや達成感の欠如」。報告タイミングは「退職を決意したとき」。円満退職のために「急な退職」「適当な引継ぎ」 「タイミングの悪い退職」は回避すべきという声多数。
引用元:エン・ジャパン
「やりがい・達成感」は仕事で自信を得ること
やりがい要因のトップ3は、「成果を認められること」「やり遂げること」「自分の成長を感じること」
引用元:マンパワーグループ
- 達成感・成功体験 → 「仕事をやり遂げた」
- 承認欲求・自己肯定感の充足 → 「認められた」「褒められた」
- 更なるやる気 → 「もっともっと成長したい」
このようにして「やりがい」と「達成感」を得られ、さらなる成長に繋がります。
しかし、このステップがうまく段階を追って踏めなければ、やる気も自信も湧き上がることがなくやがて離職に繋がっていくのです。
こちらの記事でも早期退職の理由について詳しく解説しております。ぜひご覧ください!
新入社員に「辞めたい」と思わせない対策8選

- 新入社員とのギャップを理解する
- 具体的に指示をする(内容・目的・納期等)
- 成功談ではなく失敗談とそこで得た知識を話す
- 新入社員にミスをさせない
- 成功体験のために小さな仕事から任せる
- 新入社員でも一人前として扱う
- 褒める・認める・お礼を言う
- 自分のミスを認めしっかりと謝罪する
対策1:新人とのギャップを理解する
| 上司世代の特徴 | 新入社員世代の特徴 |
| 伝えるときはメールより口頭 | デジタルネイティブのため口頭は少ない |
| 自己表現がとにかく苦手 | SNS等の影響で自己表現が得意 |
| 熱血で向上心が強い | 冷静で向上心は比較的強くない |
| 目上の存在は絶対 | 目上であっても自分の意見をしっかり言う |
| 食事も仕事の一部 | 自分の時間を大切 |
デジタルネイティブ(世代) (digital native) とは、学生時代かからインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代。
引用元:Wikipedia
特徴が必ずしも当てはまるわけではありませんが、こういった特徴の違いから、仕事や働き方・考え方の食い違いが生まれ、それが退職の引き金になることもあり得るので、頭に置いておくことよいでしょう。
対策2:具体的な指示をする(内容・目的・納期等)
会社には、社員が知らずに守っている「暗黙のルール」というものがあり、誰しも働き始めた頃はそれに振り回されることがあったかと思いますが、働いていくうちにいつしか慣れてしまい、気にしなくなっています。
特に「内容・目的・納期等」に関して新入社員に対するフォローが欠如してしまい「これやっといて」という曖昧な指示になってしまいます。
モチベーションの低下を防ぐため「内容・目的・納期」について端的に伝える事ができれば、新入社員でも自分で考えて処理することができるようになります。
対策3:成功談ではなく失敗談とそこで得た知識を話す
新入社員のモチベーションが下がってしまう大きな原因として、上司の成功談を武勇伝のように聞かされるということがあります。
「自分が若い頃は、午前2~3時まで仕事をして会社に泊まり込んで成果を上げた!」等
新入社員が取り掛かる仕事に対し、自分が新入社員のときに犯したミスや失敗を話し、そこから何を学び、どのようなことに注意すればいいのかという話をしてみましょう。
そうすれば新入社員は、ミスをしてもそこから上司のような存在になれる希望が持てるだけでなく、同じミスをしないように注意することができます。
対策4:新入社員にミスをさせない
これまでの対策1〜3にも通じますが、新入社員にはできる限りミスを起こさせないようにします。
しかしミスは必ず起こるものです。ミスからしか人は学ぶことはできませんが、実はミスの前に重要な下準備があってこそ成長することができます。
右も左もわからない、ましてや会社で働く自信なんて全くない新入社員には失敗はただただ自尊心を傷つけるだけの経験になってしまいます。
そこから早期退職に繋がってしまうので、自信がある程度育つまではミスは起こさせない工夫をしましょう。
対策5:成功体験のために小さな仕事から任せる
ミスから学び、次の成功につなげていくためには自信とプライドが必要ですが、その自信とプライドを育むためには「成功体験」必要です。
新入社員に任せられる仕事は限られていますので、プロジェクトの【ミスが出てもフォロー可能な一部分】を任せるなどして、仕事の全体像や仕事内容、プロジェクトの進め方などを学びながら、そのプロジェクトの成功にコミットさせることがポイントです。
しかし、あまりに小さな成功体験、「あれ取ってきて」や「これコピーしといて」などの単純すぎる作業は逆に人間としてのプライドを傷つけかねないので注意が必要です。
研修での経験などから「ここの部分を完成させて」とか「これどうしたらいいか、あとで意見ちょうだい」とか、少しの判断の余地があれば終わった後の達成感や、会社に対する従属感も生まれやすいでしょう。
そういった成功体験を積み重ねられれば、自信を少しずつ積み重ねられ徐々に仕事に前のめりになっていきますし、【いつか犯してしまうかもしれないミスにも対応できる力】がついてきます。
対策6:新入社員でも一人前として扱う
新入社員はまだ一人前ではありませんが、周りの社員と同じように一人前として扱いましょう。
ただし、やはり経験も何もない状態ですのでミスは必ず起こります。そのミスの質や量には細心の注意を払いつつを任せましょう。
志を高く持って入ってきた新入社員に対し、「何もできない新入社員」という画一的なレッテルを貼り続けることはその人のモチベーションを下げ、それがキッカケで生産性も著しく下がります。
その人にとってはほんの少しだけ過大評価にも見えるレッテルを貼れば、その評価に見合うよう頑張る意欲も湧いてきます。
対策7:褒める・認める・お礼を言う
成功をしたら、どんな小さなことでもそれをしっかりと認めて褒めてお礼を言いましょう。
山本五十六もそのことの重要性について言及しています。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、
引用元:Wikipedia
ほめてやらねば、人は動かじ。
山本五十六
まずは小さな仕事から任せ、その間に様々な仕事を見せ、どのように重要なのかを聞かせ、できたことにお礼を言う。
この繰り返しで、徐々に仕事を大きく任せていけば自ずと自信は生まれてきます。
可能な限り多くの人の前で褒める
褒める時、お礼を言う時はできる限り多くの人前の方が有効です。
特に他の社員の前やチーム内で褒め称えるとチームの士気もあがりますし、褒められた人は自信をつけることができます。
7回繰り返すつもりで
たとえメモを取っていたとしても、人は一度にすべてを覚えられません。
新入社員は自分なりに頭をたくさん働かせて動いていますし、必ず自分なりの信念があり、得意なことや不得意なこともあります。
「自分は新入社員の時に1回で頑張ってできたんだから、こいつも頑張ったらできるだろう。できないのは頑張ってないからだ」と自分と比較して押し付けるのではなく、その人なりのやり方でできるまで見守る意識を持ちましょう。
対策8:自分のミスを認めしっかりと謝る
「上司がミスした際にはそれを認めることができる社風かどうか」ということを新入社員は見ています。
新入社員はたくさんミスをしてしまう事もあり、注意されることに敏感になっていますので、そういったタイミングで上司が不誠実な対応をとるとすぐに信頼を失ってしまいかねません。
忘れていたことや、自分の過ちは素直に認めて謝れることは、信頼を得るための重要なポイントになります。
こちらの記事でも新入社員の退職を防ぐための対処法を解説しております。ぜひご覧ください。
若い世代との付き合い方

若者は「薄情」なのではなく「合理的」と捉える
年金需給年齢もジリジリ上がり続け、貧富の差は広がり、更にそこに老後資金不足問題が出てきて、若者は将来に不安を抱いているのが現状で、少しでも自分が安住できる地を求めるのは非常に合理的な流れだと言えます。
転職が比較的容易になっている中で、新入社員を会社に定着させ、会社の業績アップのために育てていくことは会社にとっても新入社員にとってもいいことばかりです。
コミュニケーションは「飲み」より「社内」が重要
飲みに行ったり食事に行くことで関係を深めることもできますが、若い新入社員は気を遣う社内の上司との食事などは業務の一環としてとらえています。
そんな中でもし食事に行く機会が訪れた際に、「この上司なら勉強になりそう」とか「親身に相談に乗ってくれそう」という期待感を少しでも持たせるために、社内のちょっとしたタイミングで仕事と関係のない話などをしておくといいでしょう。
そうすれば日常のコミュニケーションがスムーズになり、仕事でもいい影響が出てくることは間違いありません。
とにかく話を聞くことに徹する
普段は言われるがままに動く新入社員ですが、当然ながら色々なことを感じながら仕事をしており、中には必要以上に抱え込んでしまっている新入社員もいます。
そんな社員は一度や二度聞いただけではあまり自分の本心の話をしませんし、自分の中で改善点を探して実行しているかもしれません。
とにかく自分で抱え込んでしまうと、他の仕事でも影響してくる場合もあるので、こまめに気を遣い悩みを聞いておくことはミスを起こさせないためにも重要だと言えるでしょう。
周囲の社員の顔色もチェックしておく
新入社員だけに限らず、社内外で会う社員の顔から「疲れが出ている」「暗い」場合は注意が必要です。
1人だけでなく、複数名以上の社員を見て判断する必要がありますが、どこか疲れている表情をしたり、暗い表情をしていたりすれば何かネガティブな気持ちが溜まっている可能性が高いと考えられます。
日ごろから、社員同士の会話や、声色・顔色も見ておくようにすると社員の変化にいち早く気づくことができるでしょう。
まとめ
今回は新入社員が辞めてしまう原因と、対策について解説いたしました。
まとめるとこのようになります。
- 「やりがい・達成感」の欠如が最大の原因。仕事で自信を得れば自然と感じられる部分も多いため、自然なステップアップができるよう意識して指導しよう!
- 辞めたいと思わせないためには8つのポイントを意識しよう。特に「褒める・認める・お礼・謝罪」はいつも以上に意識をしないとできないだけでなく、ここが欠けると新入社員からの信頼は得られない。
- 若い世代をしっかりと認め、付き合い方も意識しよう。「飲み・食事」だけでコミュニケーションを図ろうとするのではなく、普段の社内から積極的にしていこう!
会社だけでなく新入社員にとっても長く働ける職場はメリットが大きいです。
常に社員が何を望み、どんな不満を抱いているのかということを考えなければ、その企業は柔軟性を失い衰退してしまう可能性が高くなります。
そうならないためにも、日頃から社員の状態をチェックし、早めに対策で人材の流出を防ぎ、会社を繁栄させていきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。