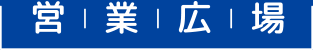こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!
と思って色々調べてみたものの、検索して出てくるものは「営業利益」や「営業利益増加率」が多く、「営業利益率」のランキングがなかなかな見当たらないのが現実です。
そこで今回は、日本企業の営業利益率ランキングと、営業利益トップ10を営業利益率に並び替えたランキングをご紹介します!
売上高と営業利益から一目で企業の「儲ける力」がわかります!
目次
日本企業の営業利益率ランキング

一般的にその企業の「儲ける力」を見たいときは、売上高に対して営業利益の占める割合である「営業利益率」を見るといいといわれています。
・営業利益:会社が本業で得た利益(大きいほうがいい)
・営業利益率:売上高に対して営業利益の占める割合
(営業利益/売上高=○○% 大きいほうがいい)
ですが、株主御用達雑誌『会社四季報』(東洋経済)にも「今期増益率」や「最高純益更新率」のランキングはあるものの、営業利益率のランキングまでは出されておりません。
そこで、まず2022年10月31日現在の「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」の3つの市場に上場している企業の営業利益率「儲ける力」ランキングのトップ10をご紹介します!
東京証券取引所は、2022年4月4日、市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編いたしました。
引用元:日本取引所グループ
ランキングは以下の通りです。
| 銘柄名 | 営業利益率 | |
| 1位 | アステリア(3853・プライム) | 116.09% |
| 2位 | 全国保証(7164・プライム) | 80.81% |
| 3位 | 手間いらず(2477・プライム) | 71.61% |
| 4位 | アサックス(8722・スタンダード) | 68.39% |
| 5位 | ジャフコグループ(8595・プライム) | 60.97% |
| 6位 | オービック(4684・プライム) | 60.50% |
| 7位 | JALCOホールディングス(6625・スタンダード) | 59.33% |
| 8位 | 日本ファルコム(3723・グロース) | 56.86% |
| 9位 | キーエンス(6861・プライム) | 55.36% |
| 10位 | 日本取引所グループ(8697・プライム) | 54.25% |
営業利益率の目安と産業別の平均は?
営業利益率のトップ10を紹介いたしましたが、これらの企業が平均から見てどれだけ営業利益率が高いのか目安として産業別の平均値をまとめてみました。
| 日本標準産業分類:大分類 | 営業利益率 |
| 建設業 | 4.02% |
| 製造業 | 2.69% |
| 情報通信 | 4.75% |
| 運輸業・郵便業 | -0.24% |
| 卸売業 | 1.66% |
| 小売業 | 1.58% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 9.35% |
| 学術研究・専門技術サービス業 | 10.0% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | -1.83% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | -0.31% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3.82% |
最も営業利益率が高い産業は「学術研究・専門技術サービス業」の10.0%、逆に最も低い産業は「宿泊業・飲食サービス業」の-1.83%となっており、やはり外出規制などの現在の状況が色濃く反映されている結果となっています。
業種業態によって大きく営業利益率は変動しますので、気になる企業の業態と比較してみてください。
こちらの記事で営業利益の計算方法について詳しく解説しております。決算書を見たら営業利益を見つけたくなりますよ!ぜひご覧ください!
営業利益率トップ3の企業は?

直近決算で営業利益率が高かったトップ3の企業を紹介いたします。
すべて株式を購入できますので、投資をお考えの方は企業情報の参考にしてみてください!
アステリア(3853・プライム)

事業の内容
システム間連携や、データ分析・マスターデータの管理を行うデータ連携ツール「ASTERIA Warp」を販売しており、9,800社以上の導入で国内シェアNo1のシェア率48%の実績があります。
その他にも、商談ツールやモバイルアプリ作成ツールなど多くの製品が好評です。
全国保証(7164・プライム)

事業の内容
特定の金融機関グループに属さない独立系の信用保証の最大手で、個人が金融機関から住宅ローンを借りる際に必要となる連帯保証人の役割を担うことが主たる事業となっています。
2022年3月末時点で提携金融機関が733機関と圧倒的な規模を誇っており、沖縄を除く全国13拠点で営業を展開しています。
手間いらず(2477・プライム)

事業の内容
「手間いらず」という複数の宿泊予約サイトを一元管理する宿泊施設向けの予約管理システムの販売が主力です。
事前に料金調整のルールを設定すれば、在庫数の増減に応じて販売価格を調整する機能にも対応しています。
予約情報をもとに、売上や稼働率など様々な角度から分析し、結果としてまとめて表示することによって、割引や価格決定の材料にもできる非常に優れたシステムです!
営業利益トップ10社:営業利益率で並び替えランキング

非常に大切なことですので、もう一度営業利益と営業利益率について確認しておきましょう!
・営業利益:会社が本業で得た利益(大きいほうがいい)
・営業利益率:売上高に対して営業利益の占める割合
(営業利益/売上高=○○% 大きいほうがいい)
営業利益は原材料(売上原価)や、人件費・広告宣伝費など(販売費及び一般管理費)の費用をかけていくと下がっていきます。
売上高 ー 売上原価 ー 販売費及び一般管理費 = 営業利益
売上高がその企業の「稼ぐ力」だとすれば、 営業利益率はその会社の「儲ける力」です。
そこで、上場企業の「営業利益」トップ10社の中で、最も「儲ける力」が強いのはどこだ?ということを調べてみました!
営業利益のランキングから各社の売上高で割り返して計算いたしました。ここからもある傾向が見えてきますよ。
営業利益トップ10社と各社売上高
| 銘柄名 | 営業利益 | 売上高 | |
| 1位 | トヨタ自動車(7203・プライム) | 2兆9956億円 (2022年3月期) | 31兆3795億円(2022年3月期) |
| 2位 | 日本電信電話(9432・プライム) | 1兆7685億円 (2022年3月期) | 12兆1564億円(2022年3月期) |
| 3位 | ソニーグループ(6758・プライム) | 1兆2023億円 (2022年3月期) | 9兆9215億円(2022年3月期) |
| 4位 | KDDI(9433・プライム) | 1兆605億円 (2022年3月期) | 5兆4467億円(2022年3月期) |
| 5位 | ソフトバンク(9434・プライム) | 9857億4600万円 (2022年3月期) | 5兆6906億円(2022年3月期) |
| 6位 | 本田技研工業(7267・プライム) | 8712億3200万円 (2022年3月期) | 14兆5526億円(2022年3月期) |
| 7位 | 日本製鉄(5401・プライム) | 8409億100万円 (2022年3月期) | 6兆8088億円(2022年3月期) |
| 8位 | 日立製作所(6501・プライム) | 7382億3600万円 (2022年3月期) | 10兆2646億円(2022年3月期) |
| 9位 | 北信化学工業(4063・プライム) | 6763億2200万円 (2022年3月期) | 2兆744億円(2022年3月期) |
| 10位 | 東京エレクトロン(8035・プライム) | 5992億7100万円 (2022年3月期) | 2兆38億円(2022年3月期) |
営業利益トップ10社の営業利益率ランキング
| 銘柄名 | 営業利益率 | |
| 1位 | 北信化学工業(4063・プライム) | 32.6% |
| 2位 | 東京エレクトロン(8035・プライム) | 29.9% |
| 3位 | KDDI(9433・プライム) | 19.5% |
| 4位 | ソフトバンク(9434・プライム) | 17.3% |
| 5位 | 日本電信電話(9432・プライム) | 14.5% |
| 6位 | 日本製鉄(5401・プライム) | 12.4% |
| 7位 | ソニーグループ(6758・プライム) | 12.1% |
| 8位 | トヨタ自動車(7203・プライム) | 9.5% |
| 9位 | 日立製作所(6501・プライム) | 7.2% |
| 10位 | 本田技研工業(7267・プライム) | 6.0% |
営業利益率ランキングからわかること
5位以上の結果を見ると、情報通信サービス業界(KDDI・ソフトバンク・日本電信電話)が並んでいます。
営業利益だけで考えると1位のトヨタには及びませんが、営業利益率=儲ける力で考えると情報通信サービス業界が安定して強いということがわかります。
会社の業績は「会社四季報業界地図」が読みやすい!

「会社四季報」も各社のHPなどに記載されているIR情報だけではわからないような情報を提供してくれているので、非常に参考になります。
今回はそんな「会社四季報」だと多少読みにくさを感じる方のために、投資や企業情報だけでなく、就活・転職に有効な業界研究などの情報も載っている「会社四季報 業界地図2023年版」を紹介いたします!
書籍概要
『会社四季報 業界地図2023年版』(発行/東洋経済新報社)は、日本の上場会社の基本情報や株価データ・業績推移など会社の成長力や投資価値の情報はもちろんのこと、就職や転職に有効な業界情報なども記載してあり、幅広い方から非常に人気があります!
価格
価格は1,430円(税込・送料無料)で、試し読みするにも非常に手が出やすい価格設定です。
こんな人におすすめ
- 株の目利き力をつけたい方
- 企業研究・銘柄発掘をしたい株・投資ビギナー
- これから就職・転職活動を行うために業界研究をしたい方
どんな本屋さんにもほぼほぼおいてある書籍ですので、立ち読み程度でも調べてみると非常に楽しいですよ!
口コミでは高評価が圧倒的
カラーで各業界が日本と世界含めてコンパクトにまとめられて見やすいです。欄外の小メモも参考になります。
引用元:楽天ブックス
コロナ禍による影響を踏まえた、各業界の今後の動向についてわかりやすくまとめられていると思います。
引用元:楽天ブックス
業界が図式化されていることや、関係性がわかりやすいなどの口コミが多く、企業や業界に興味のある老若男女すべてで高評価です!
まとめ
上場企業の「儲ける力」営業利益率ランキングを紹介いたしました。
まとめるとこのようになります。
・営業利益率トップ10企業は、業界平均よりも圧倒的に高い営業利益率を誇っている。
・営業利益率は業界によって差が出る
・営業利益トップ10を営業利益率に換算すると、情報通信サービス業が5位以内に3社と安定的に強い!
日本のトップ企業は、想像もできないような売り上げと営業利益を上げているという事がわかりました。
自分の注目している会社・業界の「儲ける力」がどれくらいあるのかを、こちらの記事で参考にしていただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました!